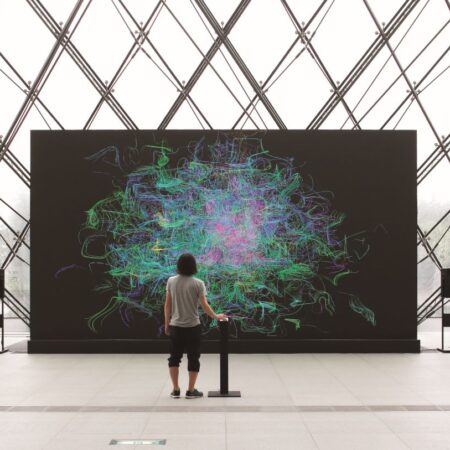音楽家 渋谷慶一郎 鍵盤とテクノロジー、生と死
聞き手・構成・文=藤田博孝(ONBEAT編集長)
2024年4月19日発行『ONBEAT vol.20』掲載
先鋭的な電子音楽作品からピアノソロ 、オペラ、映画音楽、サウンド・インスタレーションまで多岐にわたる作品を制作し、東京とパリを拠点に活動を行う音楽家・渋谷慶一郎。ボーカロイド・オペラやアンドロイド・オペラなど世界初となる作品を多数発表し、テクノロジーや生と死の境界領域について作品を通して問いかけ続ける渋谷が、その音楽的変遷を語った。
過激で先鋭的な電子音楽を創造した初期の活動
―音楽家を志したきっかけをお聞かせください。
渋谷:中学生の頃、高橋悠治さんがカフカをテーマに行ったコンサートに行きました。ステージで遊んでいるかのように自由に振舞う悠治さんを見て、僕は「何てかっこいい大人なんだろう。僕もこういうことをやりたい」と思って、音楽の道に進むことにしました。今考えれば、悠治さんは天才だからそんなことができたわけで、僕はいかに楽観的な人間なのかと呆れます。その後、僕は芸大(東京藝術大学)に入学し、三年生のときに悠治さんと詩人の朝吹亮二さんが慶應大学で行ったイベントに参加しました。そのアフターパーティーで僕は悠治さんを捕まえて2時間くらいずっと話をして、それ以降、電話でよく話すようになりました。普通、作曲家は音楽のことを音のことだけで考えがちですが、悠治さんは、それを誰とやるか、どう見せるか、つまり「どんな空間を作るか」ということを重視していて、それをある種無造作に、かつ有効に行うんです。これは大学で習っている作曲とは全く違ったことでした。悠治さんからは多くの影響を受けましたが、それは一番影響を受けた部分かもしれませんね。そして僕がまだ大学在学中の1995年に、悠治さんとのコラボレーションコンサートを「Morphe」(ミズマアートギャラリーの三潴末雄、AKI-EXの秋薫里らによって立ち上げられ、1995年から2000年にかけて、東京・青山を主な舞台として開催された。仲世古佳伸が総合ディレクションを務めた)というアートイベントで行うことになりました。コンサートはうまくいき、僕はそのコンサートの模様を収めた音源をカセットテープで販売することにしました。そこで自分で抽象画風の絵を大きな紙に描き、それをカセットテープのケースサイズに切り分けることで、一本ごとに違うジャケットカバーを作りました。そのカセットテープを渋谷のタワーレコードに持って行ったら、現代音楽の担当者が気に入ってくれて取り扱ってくれることになりました。するとそのカセットは、タワーレコード渋谷店の現代音楽部門で年間売上1位になったんです。同じ部門の売上2位がマイケル・ナイマン、3位がモートン・フェルドマンだったから、僕はまだ全く無名だったけど、音楽の世界でやっていけるかもしれないという勘違いをしたんですね(笑)。つくづく楽観的なんです。
―大学卒業後はどのような活動をされていたんですか。
渋谷:大学を卒業後の90年代後半は、ポップスのアレンジ(ザ・ブーム、高野寛、坂本美雨などの楽曲アレンジを手掛ける)をしたり、スタジオでピアノを弾いたりしていました。ところがその頃「Pro Tools」という音楽ソフトが業界に導入され、歌手のピッチをいくらでも直せるようになったんです。しかし人は修正された歌には感動しないようで、「Pro Tools」の普及後にCDの売上が明らかに落ちたんです。自分のアレンジは上手くなっている一方で、その影響で98年か99年頃にアレンジなどのギャラが下がっていきました。これは何かの暗示だなと思って、人の仕事のお手伝いでお金をもらっている場合じゃないと思いました。ちょうどその頃、ラップトップ・ミュージックが大ブームになっていたんですが、ラップトップ・ミュージシャンは僕みたいに大きなピアノを使って作曲をしたり、楽譜を書いたりしないんです。カールステン・ニコライ( 通称:アルヴァ・ノト)が日本によく来始めたときに紹介されて会ったりしたんだけど、ちょっとした合間にラップトップを開いて音楽を作っていました。その身軽さに衝撃を受けました。同時に僕たちは大変革の時期に生きてるんだと思ったんです。それで僕もコンピューターで自分の作品を作っていこうと決めたんです。またラップトップ・ミュージシャンたちは、誰にもコントロールされないように自分のレーベルを持っていることを知りました。それに強く共感したことが、後に音楽レーベルを立ち上げる動機になりました。
 |
 |
| ATAK002 Keiichiro Shibuya + Yuji Takahashi 2003 | ATAK000 Keiichiro Shibuya 2004 |
―渋谷さんは2002年に、モデルとして活躍していたmariaさんと結婚して音楽レーベル「ATAK」を設立すると、ご夫婦でラップトップ・デュオ「slipped disk 」を結成し、アルバムも発表しました。翌2003年には、高橋悠治さんとのデュオでアルバム『ATAK002』を発表しました。あの孤高のサウンドが誕生した経緯をお聞かせください。
渋谷:あの作品は僕も好きです。昔ここ(Amazon Music Studio Tokyo)の近くにあった「アップリンク渋谷」でライブ・イベントがあって、僕はゲストで出演したんですけど、当時僕はラップトップを持ってなくて、mariaのを借りて初めてラップトップでのライブを行いました。そのライブを見に来てくれた悠治さんから「なかなか面白かった。ある部分は昔のクセナキスの電子音楽を思い出した。自分は電子音楽から離れていたけど、そろそろやろうかなと思う」というメールをもらったんです。で、「それなら一緒にやりましょう」と僕が提案しました。それで、当時ワタリウム美術館で行われたカールステン・ニコライの展覧会(「カールステン・ニコライ展ー平行線は無限のかなたで交わる」2002年)の会期中に、美術館の地下にあるON SUNDAYSという施設で行われていた連続コンサートシリーズに、ラップトップのデュオで出演しました。事前の打ち合わせは一切なしで全部即興で行ったそのコンサートのライブ音源を、僕が後で編集し『ATAK002』として発表しました。あのアルバムで初めてレーベルの方向性が明確になった気がします。