
2023年1月28日(土)~2月13日(月)まで、「Study:大阪関西国際芸術祭 2023」のプログラムの一つとして、丹原健翔とヌケメのキュレーションによる「無人のアーク」が、グランフロント大阪 うめきたSHIPホールにて開催中だ。
「Study:大阪関西国際芸術祭 2023」とは
2025年に世界最大級のアートフェスティバル「大阪関西国際芸術祭」の開催を目指し、「アートとヒト」「アートと社会」の関係性や、アートの可能性を検証し学ぶ(Studyする)ためのプレイベントだ。
第2回となる今回は、関西に縁あるアーティストの展覧会をはじめ、国内外のギャラリーが出展し誰もが作品購入を楽しめるアートフェア、そしてアートの可能性を引き出すべくテーマ性を持ったカンファレンスの実施、さらにはレストランを会場に、期間限定で食とアートのコラボレーションを実現するアートダイニングなど、芸術祭会期の17日間、アートを『みる』『買う』『食す』『学ぶ』、多彩なプログラムを実施する。
この15年間で、日本では電気自動車やSNS、デジタル化といった言葉が様々な文脈で語られ、技術革新とは世界の流れに追いつくことを意味するようになった。そのようにして加速化する現代にさらに拍車をかけるように、新型感染症の世界的大流行に対応するために、我々は様々な生活の変化を受け入れるようになった。その結果、社会の土台となるコミュニケーションという行為の変化についてとどまって考える機会もないまま、誰かと関係を築くことはますます便利に、そして効率的になっていった。
現代では、一人一人が自身の物語を不特定多数に届けることができるようになり、我々は他者を消費し、他者に消費される社会の中で生きている。現代美術を代表するアンディ・ウォーホルはメディアの力によっていずれ人は皆有名人になりうる時代を60年代に予見したが、消費の行き来の中から新たなコミュニケーションの形が生まれることを彼は想像できただろうか。個々人が連なり生まれる制御のできない数々の社会のうねりや波に、アクセスしたり離れたりしながらアイデンティティについて、他者についての考えを形成していくこの時代から、この先をどう予見するべきだろうか。そして未来に何を残すべきか。この命題は当然現代美術のあり方にも影響をしている。語り継がれていくべき物語とはなにか。
本展では、うめきたSHIPホールを現代社会を航海する方舟(アーク)ととらえ、加速化する社会の中で我々にとどまることを投げかける作品たちが展示される。未来の人たちが現代を振り返るときに感じるであろうノスタルジーのような感覚をシミュレーションする、まるで廃墟のゲームセンターのような本展の成り立ちは、これからの時代のカルチャーを牽引するべく本芸術祭の姿を逆説的に示す。語り継ぐべき物語たちが閉館後の暗闇の中でも鈍い光でうめきた広場を照らす姿は、願わくばノアの方舟のように我々に社会の荒波を乗り越える助けになることだろう。
キュレーター
丹原健翔、ヌケメ
アーティスト
菅野歩美、きゅんくん、 高田冬彦、 スクリプカリウ落合 安奈、マイケル・ホー、 山形一生
キュレーター 丹原健翔 解説

中央にあるロボットアームの作品は、きゅんくんの《形骸化したロボットアーム》という作品です。アルミやアクリルを使って作っています。じっくり見ていると少し動いたりするのですが、ランダム設定なので動いていないときもあります。
この展示自体が100年後の未来から今の我々を振り返るというテーマなので、未来に残骸として残された鉄くずなどが集まった状態の中に、まだかろうじて動いてるロボットアームがあるという設定になっています。
ペラペラのアルミで弱々しく上がっているこのロボットの姿には、ある種の滑稽さや、哀れさのようなものが感じ取れるかと思いますが、逆にもっと現役バリバリな新品のロボットアームがあったとしたら、それはそれで滑稽じゃないのかなと思います。
ただ言われた通りに動くロボットアームに対して情を移せるのかというところがポイントだと思っています。作品タイトルにある「形骸化した」 という言葉は、物理的にどんどん中身が無くされて、最小限の機能しか持たなくなってしまった状態という意味にも捉えられるし、存在意義などの形骸化でもあると思います。
このロボットアーム自体が、「どういう思いでスクラップに囲まれているんだろうか?」とか、「スクラップを自分に近付けて運んだ結果として、その山の中心にいるのだろうか?」とか、「このスクラップと共に捨てられてここに残っているのか?」とか、「かつてはこういったスクラップを処理する道具として使われていたのか?」など、そのあたりの設定については、あえて曖昧な状態にしてあります。
ですから鑑賞者の方々にも、「未来にはどういったものが残るんだろう」という今回の展示のテーマについて、また新しい視点で向き合っていただければと思っています。
本展では、うめきたSHIPホールを現代社会を航海する方舟(アーク)に見立てており、「無人のアーク」展の会場には、この《形骸化したロボットアーム》を囲むように、菅野歩美の《アトビアで盆踊り》、スクリプカリウ落合 安奈の《Double Horizon》、高田冬彦の《新しい性器のためのエクササイズ》、山形一生の《無題》、そしてマイケル・ホーの《I don’t want to go, but maybe it’s for the better》という5点の映像作品が展示されています。
未来のゲームセンターのような廃墟で、2010年代、2020年代当時のそれらの映像作品たちが、人がいない中もひたすらリピートしながら流れているという設定です。それらの映像作品が、それぞれ世紀末的なコンセプトかというと一切そうではなく、むしろ家族のこと、人を思うこと、性やアイデンティティについてなど、僕からしたら100年後にも重要であり続けるだろうコンセプトを扱っています。そうした普遍的な作品たちを並べています。
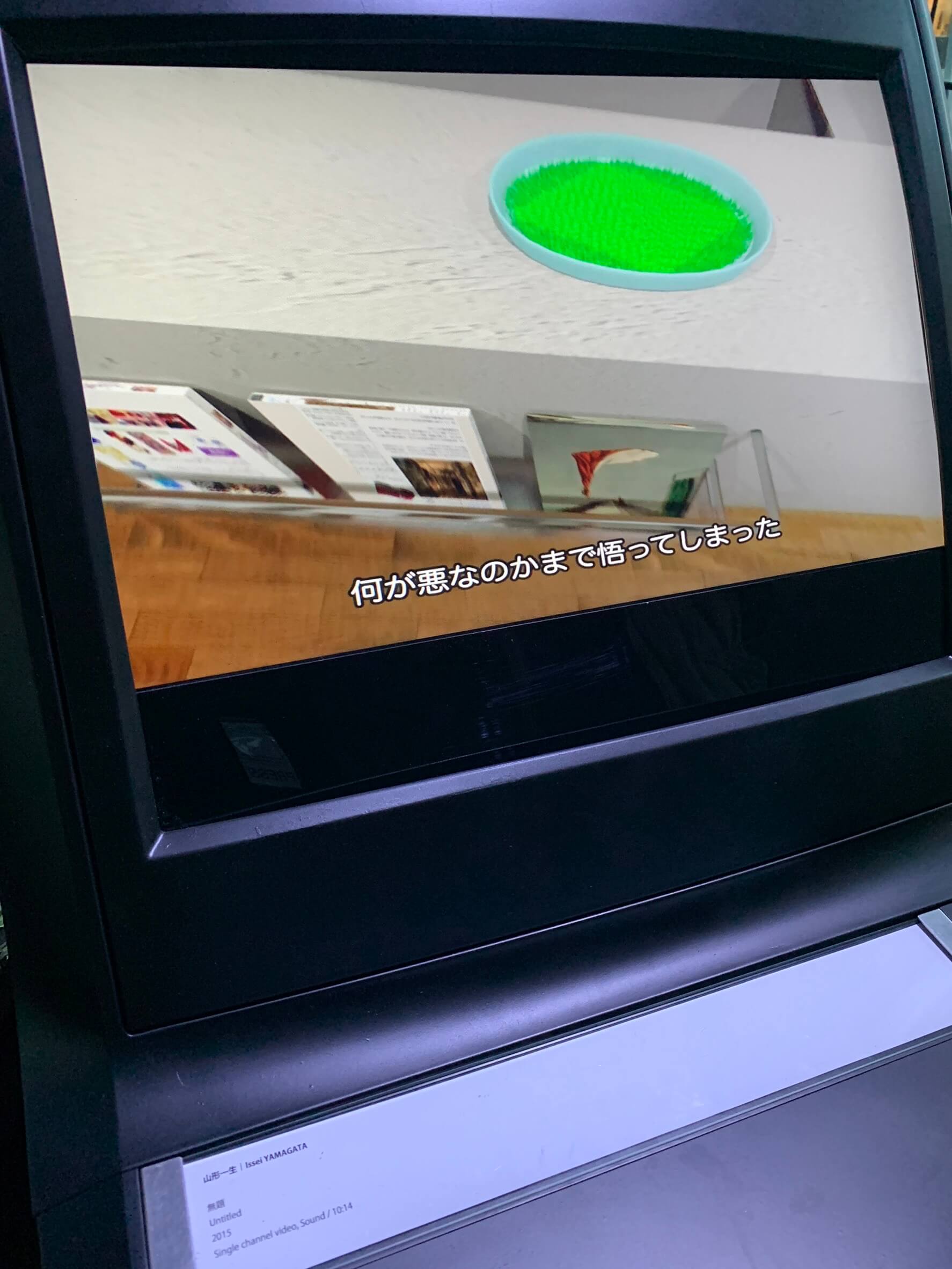
マイケル・ホーは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)を卒業しているハワイ出身のアメリカ人のアーティストです。UCLA時代に彼は、バーバラ・クルーガーに師事していました。バーバラ・クルーガーは、白黒写真の上に、フェミニズムなどをテーマにしたステートメントを赤い文字であしらった作風でよく知られています。
例えば《Untitled(Your body is a battleground》《無題(あなたの体は戦場だ)》などはとても有名な作品です。彼女に続くアーティストたちも、キャッチコピーのように端的な言葉で訴える作品を発表しています。マイケル・ホーはそういった方たちの下で学んだ後に、言葉を扱う作品を続けています。
最近の彼は、世界に対して悲観的で希望のない言葉を投げかけるような作風の作品を発表しています。今作には二つの文章があり、一つは「今あるもの以上のものを私はあなたに提供できないが、それらがいずれは役に立たなくなることを証明したい。」という文章。もう一つは「この感情は何だ?恐怖を感じるが恐れてはいない。悲しみを感じるが充実感も感じる。私は行きたくないが、そうするのが最善なことなのかもしれない。」という文章です。
何に触れているのかは曖昧にしたまま投げかける、少し切なさのあるような言葉です。最後の言葉も、自殺や死ぬ話のように捉えられるし、日本で仕事をしているアメリカ人として自身が帰国した方がいいと思っている感情なのかもしれない。あるいは、そもそもマイケル・ホーの言葉じゃなく、作品としてそいった言葉を投げかけているという可能性もあります。
開催概要
- 開催日:2023年1月28日(土)~2月13日(月)
時間:11:00〜20:00(最終日は〜17:00) ※最終入場は閉館30分前
住所:大阪府大阪市北区大深町4−20
アクセス:JR「大阪」駅 1F中央改札もしくは3F連絡橋口改札より徒歩3分
大阪市営地下鉄 御堂筋線 「梅田」駅 4番出口より徒歩1分
阪神電車「梅田」駅 百貨店改札口より徒歩5分
阪急電車「梅田」駅 2階中央改札口より徒歩5分
共通パス:不要 - 詳細はこちら
- ▼キュレーターズトーク
日時:2023年2月12日(日) 17:00〜18:00
登壇者:丹原健翔
会場:グランフロント大阪 うめきたSHIPホール

